代表挨拶・研究計画班紹介
MESSAGE
領域代表挨拶

こんにちは。
私たちの学術変革領域研究(B)「進化可能性変動史」のウェブサイトに来てくださりありがとうございます。領域の正式名称は「進化可能性の変動史を観測する科学の創成:生物情報学・進化発生学・古生物学の統合」と言います。
科学の各領域は、いろいろな成熟のフェーズにあります。生物進化の研究についても、いくつもの理論的進展や技術的革新を経て、専門化したそれぞれの領域では実に多くの理解が進んでいると言えます。しかし、私は、正確に言語化できないけれどもぼんやりとした疑問を感じていました。不正確さを承知で言うならば、「大昔の動物のほうが進化しやすかったのか?」「進化は減速しているのか?」といった問いです。たとえば脊椎動物の進化の歴史を見ると、5〜4億年前には祖先にはなかった多くの新しい器官が獲得されましたが、その後は腕がもう1対生えてくるような進化は起きていません。なんとなく不思議ではありませんか?
私には、学生時代から、物理学や宇宙論を専門とする友人が何人かいますが、彼らと話していると、宇宙の成り立ちを解き明かすために理論と実験、観測が有機的に連携していることがよく分かり、うらやましいと思っていました。「宇宙は加速膨張しているけれども、生物進化は減速してきたのかな?」、そんな、まだ科学的とは言えないような問いにいつか取り組みたいと考えていたのです。生物進化の研究でも、理論と実験はよく研究されていますが、観測はどうでしょうか?どのように観測したらいいのか分からない、現在でもそんなフェーズにありそうです。
今回、学術変革領域研究(B)に採択していただき、とても勢いがある計画研究代表者、分担研究者らとともに、この問題に取り組むことができるようになりました。それぞれがちょっとずつ異なる分野のエキスパートです。領域の正式名称の中にある「観測」という言葉には、今述べたような科学の俎上に乗り切れていない問いを科学的に探究する枠組を開拓しようという決意が込められています。宇宙の成り立ちと違って、生物進化は複雑だから難しいよね、という声もあるかもしれません。それを打開するための方法を考えるのが、この領域の使命です。科学者として新しいこと、難しいことに挑戦するのは、スリリングですが、楽しいはず。
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
(John Lennon “Imagine”)
この学術変革領域研究(B)をうまく進めて、その先にある新しい研究領域で、多くの人たちと一緒に、生物進化の理解を進めるための理論と実験、観測の統合研究が展開できるようになることを願っています。
– 平沢 達矢(領域代表)
Our Teams
研究計画班紹介
A01 – 平沢班

平沢 達矢(東京大学)
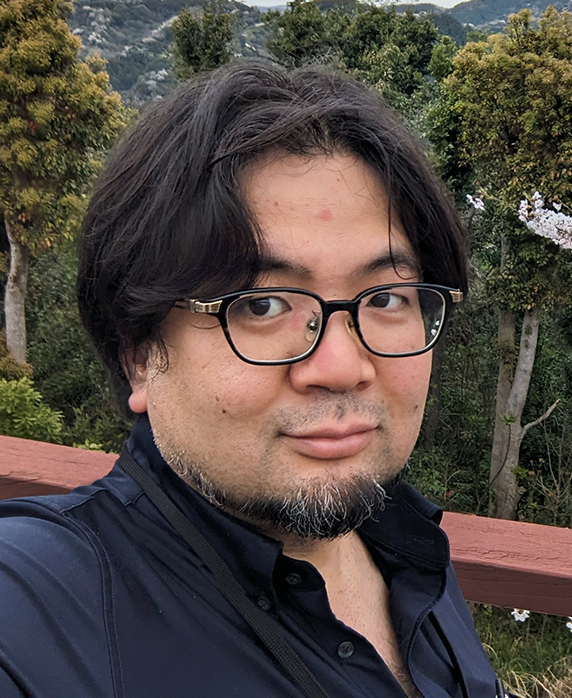
分担者:東山大毅(総合研究大学院大学)

分担者:木村 由莉 (国立科学博物館)

古生物学と進化発生学の統合研究で明らかにする脊椎動物形態進化の黎明期
脊椎動物の形態進化について、主に化石記録をもとにした形態進化過程の解明とそれらの背後にある発生機構の特定を進め、数億年スケールに注目した際の進化的新規形質の成立のしやすさの時間変化(世代変化)や、種分化スケールに注目した際の形態特徴量の集団内変異量の時間変化についての実証データを集めます。
それらのデータをもとにして、特に発生拘束(発生機構に内在する表現型の変異性の制限)の変動史や、形態特徴量の集団内変異パターンと発生の可塑性の関係性に注目して、進化可能性の変動を検証していきます。
A02 – 上坂班
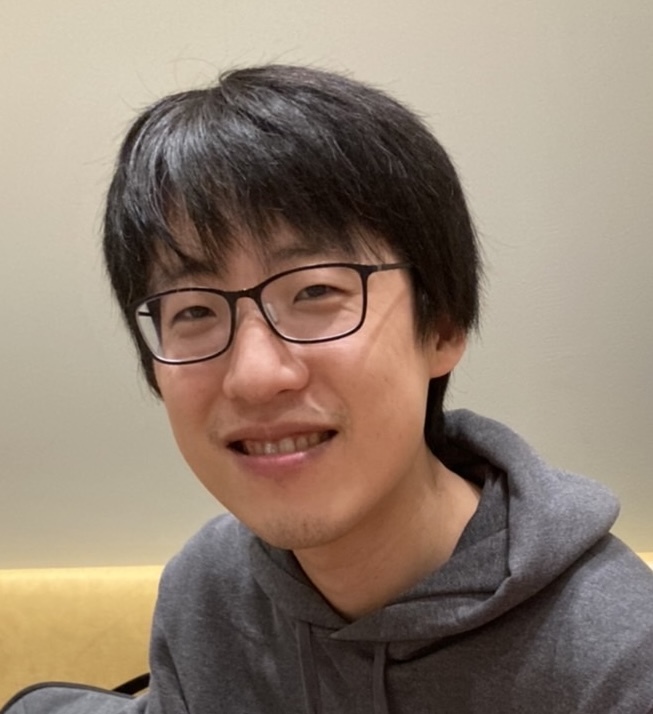
上坂 将弘 (東北大学)

深層学習による形態予測から迫る鳥類の翼の進化可能性変動史
脊椎動物の鳥類前肢に着目し、器官発生に関わる遺伝子発現制御と形態の進化可能性がどのように変遷してきたかを理解することを目指します。
本研究では、比較オミクス解析と深層学習を駆使して、遺伝子型の変化による表現型の変化を定量的に測定するアプローチを開発します。この手法を応用して、遺伝子発現制御や前肢形態の進化可能性がどのように進化してきたのか、そこに一般傾向や法則は存在するのかを明らかにします。
A03 – 安藤班

安藤 俊哉 (京都大学)
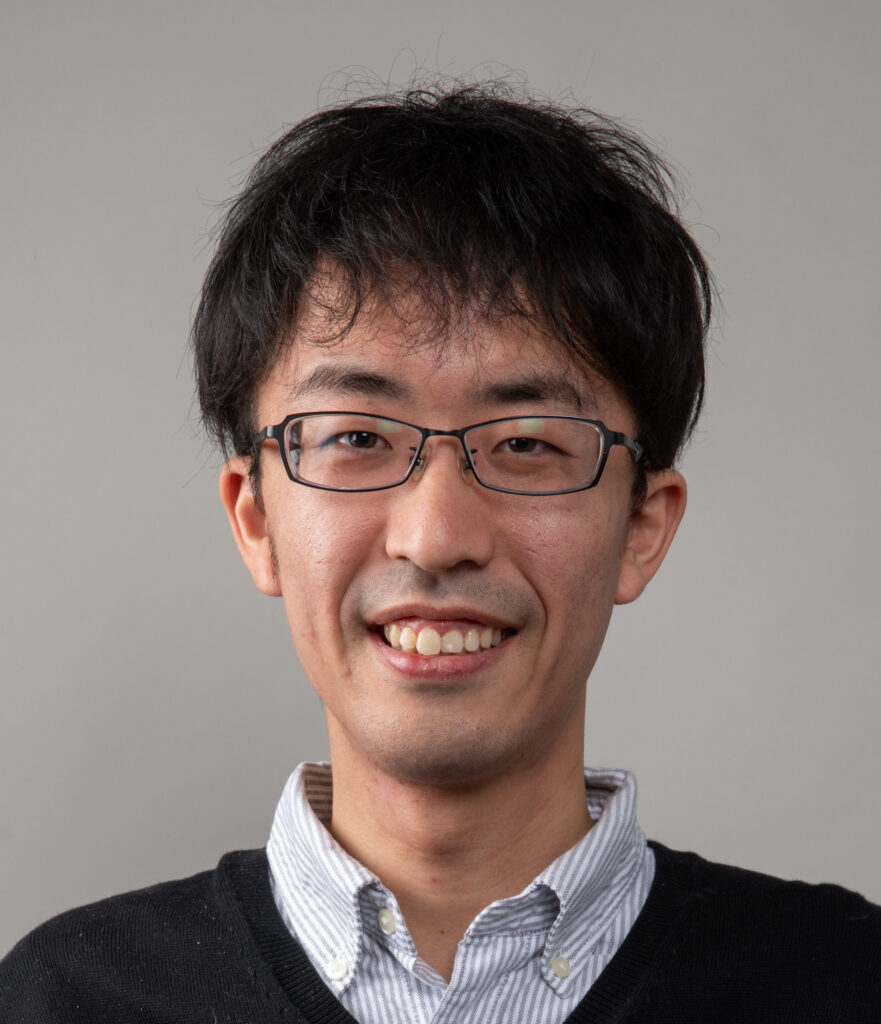
分担者:安齋 賢 (岡山大学)

昆虫・魚類の色彩平行進化における進化可能性変動史
異なる系統で種内多型の平行進化を引き起こす鍵遺伝子(平行進化遺伝子) に着目します。平行進化遺伝子における変異パターンを実験室内で復元する独自の実験遺伝学手法を駆使した「進化の起源となる変異を復元し進化可能性を測定する」アプローチを開拓します。
本手法を通じて、多細胞生物の異なる系統で種内・種間レベルの平行進化を引き起こす法則性や、大規模な染色体構造転換を含む様々な変異の蓄積による適応度の低下を乗り切る戦略を解明します。
